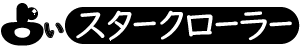パワースポット
浅草寺|東京都のパワースポット
浅草寺

浅草寺の創建は推古天皇の時代の628年で、東京都最古の寺とされる。628年3月18日の早朝、現在の隅田川で漁をしていた兄弟の網に仏像がかかった。この土地の長であった土師中知は、その聖観世音菩薩像の礼拝供養のために出家して自宅を寺に改めた。これが浅草寺の始まりという。

浅草寺の御本尊は、聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)。いわゆる観音さまは、誰にでも分け隔てなく救いの手を差し伸べて、あらゆる願いを聴いてくださる慈悲深い仏さま。

観音を信仰していた源頼朝は、1180年に平家追討のために下総から武蔵国へ入ったときに、浅草寺で戦勝祈願している。また、1189年に奥州藤原氏を征討に向かう際にも、戦勝祈願のために浅草寺に田園36町を寄進している。

江戸時代には、徳川家康が浅草寺を祈願所に定めて寺領五百石を与えるなど、徳川将軍家に重んじられた。1631年と1642年には火事で焼失したが、3代将軍徳川家光の援助によって再建された。

1685年には、表参道に商店が設けられた。これは、近くの住民に掃除をしてもらう代わりに、表参道で商売することを許可したというもの。これがのちの「仲見世」となった。
浅草寺の住所
〒111-0032
東京都台東区浅草2-3-1
TEL 03-3842-0181
浅草寺への交通アクセス
浅草駅から徒歩すぐ