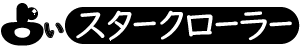パワースポット
亀戸天神社|東京都のパワースポット
亀戸天神社

亀戸天神社は、菅原道真を祀る天満宮。学問の神様として親しまれており、受験シーズンになると受験生の参拝者が増える。

亀戸天神社の歴史は、九州太宰府天満宮の神官であった菅原道真の末裔が、神のお告げにより菅原道真ゆかりの飛び梅の枝で天神像を刻んだことに始まる。

この天神像を祀る社殿を建立することを志して、ふさわしい土地を求めて九州から諸国をめぐる旅に出た。やがて江戸にたどり着いた彼は、亀戸村に元からあった小さな祠に1661年に天神像を祀った。

1662年になり、4代将軍徳川家綱の指示で、太宰府天満宮にならって社殿、回廊、心字池、太鼓橋などが造営された。徳川家綱は、もともと天神様を篤く信仰しており、現在の亀戸天神社が建っている土地を社殿造営のために寄進した。

亀戸天神社は、藤と梅の名所として昔から知られる。安藤広重の『名所江戸百景』にも、太鼓橋を背景にした藤の花が描かれている。
亀戸天神社の住所
〒136-0071
東京都江東区亀戸3-6-1
TEL 03-3681-0010