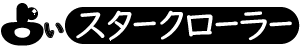パワースポット
東寺|京都府のパワースポット
東寺

東寺は、国家鎮護のために平安京の東西に「東寺」と「西寺」を建立する計画から、796年に官寺として建立された。

823年、嵯峨天皇は、真言宗の宗祖である空海に東寺を下賜(かし)された。その後は国家鎮護の寺であると同時に、真言密教の根本道場として栄えた。上の写真は金堂だが、空海が住房を構えていたのは御影堂(大師堂)と伝わる。

東寺は、教王護国寺(きょうおうごこくじ)とも呼ばれる。「王を教化して国を護る寺」であり、歴代天皇から篤く信仰されている。鎌倉時代になると弘法大師信仰が高まり、庶民からも信仰を集めるようになる。また、足利尊氏・豊臣秀吉などの時代の権力者からの庇護を受けて栄えた。

東寺は、建造物・彫刻・絵画・工芸品・書など多数の国宝を所蔵しており、建物では金堂・五重塔・大師堂などが国宝に指定されている。また、通常は絵画で描かれる曼荼羅を、仏像彫刻の配置で立体的に表現した立体曼荼羅など、見どころが多い。

空海が3月21日に亡くなったことにちなみ、東寺境内で「弘法市」が開かれるようになった。当初は年一回であったが、1239年以降は毎月開かれるようになったとされる。現在も毎月21日は弘法大師の縁日として、東寺境内で早朝から夕方まで「弘法市」と呼ばれる骨董市が開かれている。
東寺の住所
〒601-8473
京都府京都市南区九条町1
TEL 075-691-3325