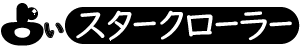パワースポット
鞍馬寺|京都府のパワースポット
鞍馬寺

鞍馬寺は、京都盆地北部の鞍馬山(標高584m)の南斜面にある寺。鞍馬山の東側に鞍馬川、西側に貴船側が流れている。2つの川は貴船口で合流するが、この貴船口から東側の鞍馬川沿いに上流へ進むと鞍馬寺へと至る。ちなみに、西側の貴船川沿いに上流へ進むと貴船神社へと至る。

鞍馬寺は、770年に鑑真の弟子の鑑禎(がんてい)によって開かれた。夢のお告げで鞍馬山に登った鑑禎は、鬼女に襲われたところを毘沙門天に助けられた。そこで、毘沙門天を祀る草庵を結んだという。

796年、藤原 伊勢人(ふじわらのいせんど)は、かねてから観世音を祀りたいと願っていたが、夢のお告げで鞍馬山に導かれて登ったところ、そこには鑑禎が毘沙門天を祀る草庵があった。再び夢で「毘沙門天も観世音も根本は一体」と告げられたため、伽藍を建立して毘沙門天像と千手観音像を祀った。

鞍馬山は牛若丸(源義経)が修行をした地として知られる。能の演目「鞍馬天狗(くらまてんぐ)」は、牛若丸が鞍馬山で天狗に出会い、天狗から兵法の奥義を伝授されたとする話。

鞍馬寺は、1949年(昭和24年)までは天台宗に属していたが、1949年以降は独立して鞍馬弘教総本山となっている。
鞍馬寺の住所
〒601-1111
京都府京都市左京区鞍馬本町1074
TEL 075-741-2003