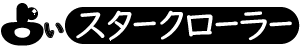パワースポット
貴船神社|京都府のパワースポット
貴船神社

貴船神社の創建は、反正天皇(はんぜいてんのう)の時代と伝わる。伝承では玉依姫命(たまよりびめ)が黄色い船に乗って淀川・鴨川・貴船川と上流へさかのぼり、この地に水神を祀ったという。この時の「黄船」が「貴船」の由来。

もし反正天皇時代の創建なら、5世紀前半頃となる。677年には社殿造替の記録が残る。他に、796年に貴船神社の神が藤原伊勢人(ふじわらのいせんど)の夢にあらわれて、鞍馬寺を建立するよう告げたという記録が残るので、遅くともこの時代には貴船神社が崇拝されていたことがうかがえる。

貴船神社は、貴船山と鞍馬山に挟まれた山深い地に鎮座する。神社前を流れる貴船川は鞍馬川に合流して、やがて賀茂川に合流する。さらに賀茂川は高野川と合流して京都の中心を流れる鴨川となる。貴船神社は、都の水源を祀った神社と言える。

主祭神は、高龗神(たかおかみのかみ)という水神。古代には、干ばつには黒馬、長雨には白馬を奉納して祈願したという。やがて馬形の板を奉納するようになり、これが現在の絵馬につながっているため、貴船神社は絵馬発祥の神社とされることがある。

鞍馬貴船町や貴船川などの地名には「くらまき ぶ ねちょう」「き ぶ ねがわ」と濁音が付くが、貴船神社は清らかな水神を祀った神社であることから「き ふ ねじんじゃ」と濁らない。
丑年の丑月の丑の日の丑刻に貴船明神が貴船山に降臨したという伝承から、願いが聞き届けられるように丑の刻参りが行われた時代もあったようだが、現在は夜間閉門されるので貴船神社で丑の刻参りは行えない。
貴船神社の住所
〒601-1112
京都府京都市左京区鞍馬貴船町180
TEL 075-741-2016