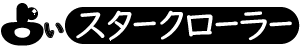パワースポット
榛名神社|群馬県のパワースポット
榛名神社

榛名神社は、586年に祭祀の場が創建されたのが始まりと伝わる。榛名山の神を祀る神社で、古来より榛名山を信仰する修験者の霊場であった。境内からは、9世紀ごろの寺院跡の巌山遺跡が見つかっている。

境内には、御姿岩(みすがたいわ)・九十九折岩(つづらおれいわ)・倉掛岩(くらかけいわ)・鉾岩(ぬぼこいわ)などの巨岩があり、独特の景観をつくる。

本社は、御姿岩(みずがたいわ)と呼ばれる岩壁とつながっている。御姿岩内の洞窟は神聖な本殿であり、そこに御神体が祀られている。主祭神は火の神と土の神で、鎮火や五穀豊穣にご利益があるとされる。また、開運全般や商売繁盛にご利益があるとされる。

境内には、矢立杉(やたてすぎ)と呼ばれる推定樹齢600年、高さ55mの杉の巨木が立つ。武田信玄が戦勝祈願のため、杉に矢を射る矢立神事をおこなったことに由来する名称とされる。

榛名神社の住所
〒370-3341
群馬県高崎市榛名山町849
TEL 027-374-9050