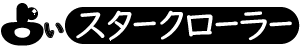パワースポット
日御碕神社|島根県のパワースポット
日御碕神社

日御碕神社は、上の宮と下の宮の上下2社からなり、両社を総称して「日御碕神社」と呼ぶ。上の宮は「神の宮」であり、素盞嗚尊(すさのおのみこと)が祀られている。

下の宮は「日沈宮(ひしずみのみや)」であり、天照大御神(あまてらすおおかみ)が祀られている。

上の宮の創建はかなり古くて不詳(社伝では紀元前536年)だが、下の宮は948年に村上天皇の勅命で造られた。この際、「伊勢神宮は昼を守り、日御碕神社は夜を守る」とされたことが「日沈宮」という名称の由来。

出雲の国造りを終えたスサノオは、「私の魂はこの柏の葉がとまる所に住もう」と占った。風に舞った柏の葉は、当社背後にある隠ヶ丘(かくれがおか)に降りたという。この言い伝えから、当地はスサノオ終焉の地として信仰されている。(スサノオ終焉の地は「須佐神社」とする説もある)

出雲大社の御祭神である大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)は、スサノオの息子である。スサノオ終焉の地として祀られている日御碕神社は、「出雲大社の祖神(おやがみ)さま」としても崇敬されている。
日御碕神社の住所
〒699-0763
島根県出雲市大社町日御碕455
TEL 0853-54-5261