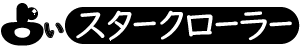パワースポット
出雲大社|島根県のパワースポット
出雲大社

出雲大社は、正式には「いづもおおやしろ」だが、一般には「いずもたいしゃ」と呼ばれることもある。住所は出雲市大社町(いずもしたいしゃちょう)であり、最寄り駅は一畑電車の出雲大社前駅(いずもたいしゃまええき)である。

出雲大社の始まりは、日本神話で語られている。この地域を治めていた大国主が大和政権に国譲りする際、自分の住処として立派な宮を造ることを条件にして、それに従って天之御舎(あめのみあらか)が造られた。

実際の創建年は不詳だが、かなり古い時代の創建であるのは間違いない。例えば、崇神天皇60年(BC38年)に出雲大社の神宝にまつわる事件が起きたことや、斉明天皇5年(659年)に出雲大社が修造されたことなどが『日本書紀』に記述されている。

現在の本殿は、江戸時代の1744年に造営されたもので国宝に指定されている。他に、楼門・八足門・銅鳥居など22の建造物が重要文化財に指定されている。拝殿は、室町時代に造営されたものであったが、1953年に残り火の不始末から焼失してしまった。現在の拝殿は1959年に造営されたもの。

大国主が国譲りの際にのぞんだのは「太く深い柱を使い、千木(ちぎ)が空高くまで届く宮」であった。現在の本殿の高さは約24mだが、出雲大社の宮司家に伝わる平面図によれば、古代の本殿は3本の大木を鉄輪で束ねて一本の柱としており、高さは16丈(約48m)あった。2000年(平成12年)には、実際に境内から3本束ねの柱が発掘されている。
出雲大社の住所
〒699-0701
島根県出雲市大社町杵築東195
TEL 0853-53-3100