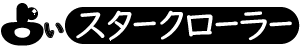パワースポット
大崎八幡宮|宮城県のパワースポット
大崎八幡宮

大崎八幡宮は、社伝によれば奈良時代末から平安時代初期に、坂上田村麻呂が宇佐神宮を現在の岩手県奥州市に勧請したことに由来している。

その後、室町時代に奥州管領の大崎氏によって現在の宮城県大崎市に遷され、さらに江戸時代初期に伊達政宗によって現在の宮城県仙台市に遷された。

現存する社殿は、1607年に伊達政宗の寄進によって建立されたもの。当時豊臣家に仕えていた工匠を招いて造営されたものであり、豪壮かつ華麗な桃山建築の特色があらわれている。本殿・石の間・拝殿は、国宝に指定されている。

大崎八幡宮の祭神は応神天皇・仲哀天皇・神功皇后で、特に戦勝祈願にご利益があるとされる。また、開運招福・商売繁昌・合格祈願・家内安全・安産祈願などにもご利益がある。

大崎八幡宮の住所
〒980-0871
宮城県仙台市青葉区八幡4-6-1
TEL 022-234-3606
大崎八幡宮への交通アクセス
JR仙台駅ルから仙台市営バス20分「大崎八幡宮前」下車