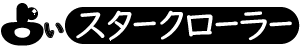パワースポット
熊野速玉大社|和歌山県のパワースポット
熊野速玉大社

熊野速玉大社は、景行天皇58年(西暦128年)に現在地に造営されたと伝わる。歴史ある熊野三山のなかでも、最も古い歴史をもつ神社のひとつと言える。

主祭神は、熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)・熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)の2神で、それぞれ「いざなぎのみこと」「いざなみのみこと」を表す。

境内には、御神木の梛(なぎ)がある。推定樹齢1000年、高さ20mの大樹であり、梛の木としては国内最大の可能性が高い。

梛の木は古来から、縁結び・災難除け・神様の化身とされる。帰路の無事を願って「熊野の宮のなぎの葉」をお守りにいただくのが習わしであった。

梛の葉は引っ張っても切れにくいため、縁結びのお守りにされる。例えば、北条政子は鏡の下に梛の葉を敷いて源頼朝との逢瀬を祈ったと伝わる。
熊野速玉大社の住所
〒647-0003
和歌山県新宮市上本町1-1
TEL 0735-22-2533