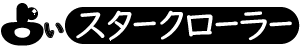パワースポット
飛鳥寺|奈良県のパワースポット
飛鳥寺

飛鳥寺は、596年に蘇我馬子(そがのうまこ)が創建した日本初の本格的な仏教寺院。かつて、飛鳥の里は天皇が住まわれた首都であり、6世紀末から7世紀末までの約100年の間、飛鳥寺を中心にして文化や芸術が栄えた。

当時は、現在の約20倍という壮大な規模の寺であったが、鎌倉時代に伽藍の大半を焼失した。現存する本堂は江戸時代の1826年に再建されたもので、現在はのどかな田園風景のなかにひっそりと佇んでいる。

御本尊の飛鳥大仏は、飛鳥時代の作で日本最古の仏像とされる。この仏像の作者・鞍作止利(くらつくりのとり)は、聖徳太子の命を受けて多くの仏像制作に従事した人物で、法隆寺金堂の釈迦三尊像の作者ともされている。

飛鳥寺では、自由に鐘を撞くことができる。連打は禁止されており、鐘楼には「上は有頂天より下は奈落の底まで 響けよかしと念じて静かに一度」という木札が掲げられている。

寺の西側には「蘇我入鹿の首塚」がある。蘇我入鹿は、645年の乙巳の変(大化の改新)で、飛鳥板蓋宮の大極殿において首をはねて暗殺された。はねられた首が飛んで鎌足を追いかけまわしたという伝説があり、蘇我入鹿を恐れて供養するための首塚とされる。
飛鳥寺の住所
〒634-0103
奈良県高市郡明日香村飛鳥682
TEL 0744-54-2126
飛鳥寺への交通アクセス
近鉄「橿原神宮前駅」からバス20分、「飛鳥大仏前」バス停から徒歩2分