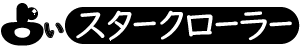パワースポット
長谷寺|奈良県のパワースポット
長谷寺

長谷寺の創建年は不詳だが、8世紀前半の奈良時代の創建とされる。寺伝によれば、686年に道明(どうみょう)が三重塔を建立して、727年に弟子の徳道(とくどう)が霊木で造った十一面観音像を祀ったと伝わる。

平安時代には、観音霊場として貴族の信仰を集めた。藤原道長が1024年に長谷寺に参詣した記録が残る。鎌倉時代以降は、武士や庶民からも信仰を集めるようになった。

長谷寺の伽藍は、初瀬山の山麓から中腹にかけて配置されている。入口の仁王門から399段の屋根付きの階段を上って本堂へと至る。この登廊(のぼりろう)は、平安時代の1039年に造られたもので、重要文化財に指定されている。

本堂は、1650年に徳川家光の寄進で再建されたもので、国宝に指定されている。初瀬山の断崖絶壁の南面に懸造りで造られた建物で、眺めの良い舞台が設けられている。内部には御本尊の十一面観世音菩薩立像(重要文化財)が安置されている。室町時代の1538年に運宗らによって制作された像で、高さが約10mもある木造の仏像は国内最大とされる。

長谷寺は、枕草子・源氏物語・更級日記など、多くの古典文学に登場する。今昔物語集や宇治拾遺物語に収録されている昔話『わらしべ長者』は、長谷寺を舞台にしたお話。長谷観音に参詣した男が、その帰りに大門(仁王門)のところで転び、手に触れた一本の藁を観音様の下さったものとして持ち帰ったところ、それが最終的には屋敷と田んぼになったというあらすじ。
長谷寺の住所
〒633-0112
奈良県桜井市初瀬731-1
TEL 0744-47-7001