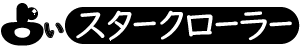パワースポット
法隆寺|奈良県のパワースポット
法隆寺

法隆寺は、推古天皇の時代の607年に創建されたと伝わる。605年、聖徳太子は飛鳥から斑鳩(いかるが)の里に移住した。移住から2年が過ぎた607年、聖徳太子は自分の住んでいた斑鳩宮のとなりに斑鳩寺を造営した。これが法隆寺の元になっており、いまでも法隆寺を別名「斑鳩寺(いかるがでら)」と呼ぶことがある。

法隆寺は、現存する世界最古の木造建築物として知られる。天智天皇の時代の670年に法隆寺が全焼したという記録が日本書紀にあり、発掘調査の結果からも一度焼失した後に再建された跡があったため一度は焼失している可能性が高い。ただし、仮に670年に焼失していたとしても、693年には法隆寺で国家鎮護などを祈願する仁王会が行われているので、遅くともこの頃には再建されている。

五重塔の高さは約32.5m、現存する世界最古の木造五重塔となっている。長い歴史のなかで経験した地震でも倒れたことがないのは、五層を貫く心柱が横揺れを吸収することが大きい。五重塔は仏舎利(釈迦の遺骨など)を安置するストゥーパに起源があるが、法隆寺の五重塔の中心地下にある礎石には穴が穿たれており、そのなかにはガラスの舎利壺、金や銀を使用した舎利容器などが納められている。

法隆寺には、金堂・五重塔・中門・夢殿をはじめとして、国宝に指定されている建物が数多くあるが。回廊もまた国宝に指定されている。

739年、聖徳太子の宮跡に八角形のかたちをした夢殿(ゆめどの)が建立された。夢殿には、聖徳太子の等身像と伝わる救世観音像が安置されている。法隆寺は、金堂や五重塔がある西院伽藍と、夢殿がある東院伽藍に分けることができる。西院伽藍は、聖徳太子が建立した斑鳩寺が発展したもの、東院伽藍は聖徳太子が住んでいた斑鳩宮の跡地に夢殿などが建立されたもの。
法隆寺の住所
〒636-0115
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
TEL 0745-75-2555