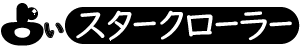パワースポット
東大寺|奈良県のパワースポット
東大寺

東大寺は、8世紀前半に聖武天皇が主導して建立された寺。その少し前に若草山の麓に創建された金鍾寺(こんしゅじ)を前身にして、盧舎那仏(るしゃなぶつ)や大仏殿が建造された。史料に「東大寺」の名称が最初に登場するのは、大仏鋳造が進められている最中の748年である。

743年に聖武天皇が大仏造立の詔を発し、747年に大仏の鋳造が始まり、752年に大仏の鋳造が完了して開眼会(かいげんえ)が行われた。そして、大仏鋳造完了後に大仏殿の建設工事が始められ、758年に大仏殿が完成した。尚、現存する大仏殿は、1709年に再建されたもの。廬舎那仏は、ほとんどの部分が後の時代に修復されたものだが、台座(蓮華座)などの一部には創建当初のものが残っている。

東大寺の南大門は、平安時代に台風で倒壊している。現在の南大門は、鎌倉時代の1199年に再建されたもの。門の左右には、1203年に造られた木造の金剛力士立像が安置されている。門に向かって左が口を開いている阿形(あぎょう)、右が口を閉じている吽形(うんぎょう)。阿形像・吽形像の二体は運慶が中心となって、快慶らとともに制作された。

東大寺は、二度焼失している。一度目の消失は、1181年に平氏が行った南都焼討(なんとやきうち)による。1195年に大仏殿が再建され、その法要には源頼朝が列席している。二度目の消失は、1567年の東大寺周辺で繰り広げられた松永久秀と三好三人衆の戦いによる。二月堂は、二度の大火には焼け残ったが、江戸中期にお水取りの火がもとで焼失したため1669年に再建された。

法華堂(ほっけどう)は、寺伝によれば東大寺以前にあった金鍾寺の遺構とされる。東大寺のなかでも最古の建物であり、創建時期は奈良時代の740~748年頃と推定される。旧暦3月に法華会(ほっけえ)が行われていたことから、一般的には「三月堂」と呼ばれる。堂内には、奈良時代に制作された天平彫刻が安置されており、その多くが国宝。以前には日光・月光菩薩立像なども安置されていたが、これらは東大寺ミュージアムに移動した。