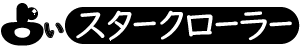パワースポット
真清田神社|愛知県のパワースポット
真清田神社

真清田神社の創建は不詳だが、その歴史は古く、尾張地方を治めた尾張氏が神仏を祀ったことに始まるとされる。遅くとも平安時代には、「尾張国の一宮」として国司をはじめ人々の崇敬を集めていた。

社伝によれば、御祭神の天火明命(あめのほあかりのみこと)は、神武天皇33年3月3日(BC628年)に当地に鎮座したとされる。天火明命は尾張氏の祖神(おやがみ)で、太陽や農業の神様として信仰されている。

1945年(昭和20年)の空襲で社殿が焼失したため、現在の本殿は戦後の1954年(昭和29年)に再建されたもの。また、拝殿は1956年(昭和31年)の再建。

楼門は空襲による焼失を免れたが、現在の楼門は1961年(昭和36年)に再建されたもの。

真清田神社の鎮座する地域は、古代から木曽川の恩恵を受けて発展してきた。真清田(ますみだ)という名称は、清く澄んだ木曽川の水を灌漑利用して水田を形成してきたことに由来する。
真清田神社の住所
〒491-0043
愛知県一宮市真清田1-2-1
TEL 0586-73-5196